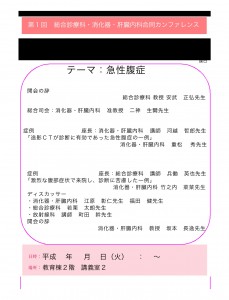文字の大きさを変更できます
タイトル
スタッフ日記
9月25日抄読会
9月25日の抄読会は研修医2年目の後藤が担当でした。好きな論文で良いとのことだったので、Anti-Acid Therapy and Disease Progression in Idiopathic Pulmonary Fibrosis: an analysis of data from three randomized controlled trials,Lancet Respir Med. 2013 July ; 1(5): 369–376.doi:10.1016/S2213-2600(13)70105-Xを読んでみました。特発性肺線維症(IPF)の患者さんでは胃食道逆流を合併している人が多く、この症状が原疾患増悪の危険因子である可能性が示唆されています。この論文は胃食道逆流の治療である抗酸療法(PPI、H2blocker)と原疾患の進行との関連ついて検討したものです。結論としては、抗酸療法はIPFの患者においてFVCの低下を遅らせ、急性増悪の減少するのに関与している…ということなのですが、後ろ向き研究であることやPPIの長期内服による不利益など、この結果を実際の治療にどう生かしていくのかにはまだまだ考えなければならない事が多数あると思われました。「IPFの患者さんになぜ胃食道逆流が合併しやすいのか?」「どんな検定を使用しているのか?」など先生方から色々と質問もしていただき、改めて調べてみたい事ができるなど、良い勉強の機会をいただけたと思いました!






2014/9/28
Conference about Acute Abdomen on 21st Oct.
Journal Club on 11th, Sept. All in all, Troponin-T!
前後してしまいましたが、9月11日の抄読会は安武教授の当番で、Troponin elevation in coronary vs. non-coronary disease. European Heart Journal (2011) 32, 404-411でした。教授が抄読会で発表するってのはあまり行われていないのではないでしょうか。教授があえてみんなに教え込まないといけないのは、心電図では判断できない微妙なACSが総診であまりに多いからだと思われます。高感度Trop-T、判断に困ることありますよね。迅速判定キットが陽性だったらすぐさま循環器の先生を呼びますが、正常よりちょい高い、心電図変化なし、胸痛いような痛くないような。まあ結論としては、症状、心電図、エコーなどいろいろ調べて総合的に判断しましょうということです。読んでみてください。
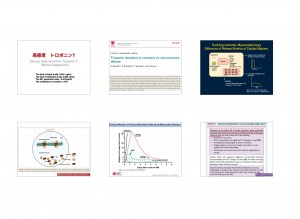
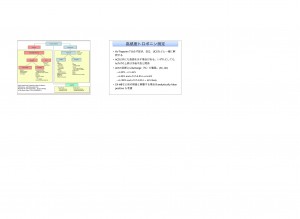
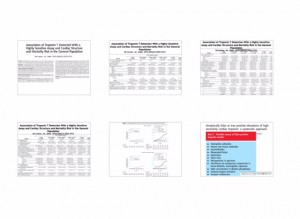
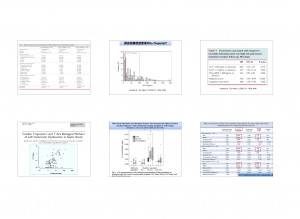
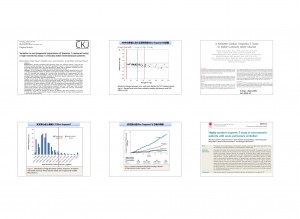
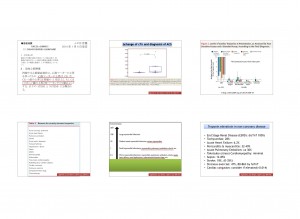
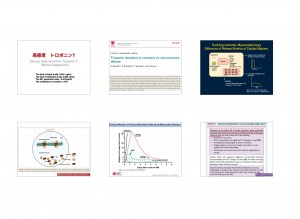
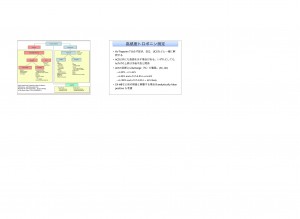
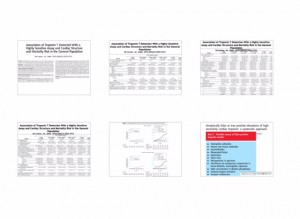
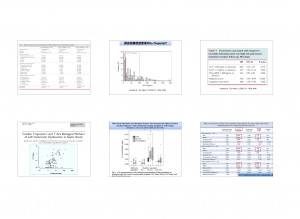
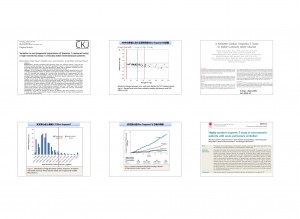
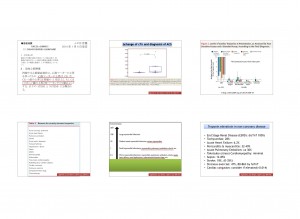
2014/9/24
Today’s Journal club
Facebookに不具合が発生していて、更新できませんでした。お待たせしました!
本日の抄読会は小原先生担当で、Laboratory Measurement of the Anticoagulant Activity of the Non-Vitamin K Oral Anticoagulants (J Am Coll Cardiol 2014;64:1128-39)でした。はやってますね、NOAC。私たちは外傷患者を診察することも多いので、血液サラサラの薬を飲んでいるかどうかは常に気にしています。この論文では、「NOACはワーファリンと違って何もはからなくていいって言われているけど、出血してるときや手術前、overdoseや怠薬が疑われるとき、高齢者や腎機能障害のある患者はやっぱなにかパラメーターがあったほうがいいよね、何がいいだろうね」というテーマのシステミックレビューでした。結局ダビガトラン飲んでる時にトロンビン時間はちょっといいかもよ、という結果。難しい…Figure
2014/9/18